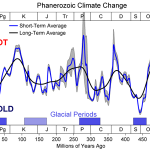豊橋までは出向かないものの、
先日と似たようなルートで出張。
まずはR151で新城へ向かいます…が!
朝から電話が鳴り響き…
朝鳴る電話ってのは、至急対応案件の可能性が高い。
お恥ずかしながら、出張先に遅刻(汗
午前中の会議を経て、午後からはR257と県道32を経由して
新城市街と設楽町の中間点。
橋梁の上部工や下部工を確認。
改めて、橋梁って架設年次によって構造に流行があるなあと。
今回拝見した橋梁、舗装路面はコンクリートで、
その骨材に玉砂利を使用。

玉砂利舗装も流行った時期があるようで、
路面強度が高い方法なんですが、補修を行うのは大変。
通常、橋梁の舗装路面を修繕するときは、削って舗設ですが、
切削機で削るのが困難。
高度経済成長期のインフラにありがちですが、
それ自体が劣化すること、補修がいずれ必要になること、
考えられていない構造物がたくさんあります。
上記の橋梁よりも古く、年代物の橋梁もありましたが、
こちらの方が床版の損傷は少ない。

道路構造物の損傷劣化は、経年よりも、重交通による影響の方が大きい。
道路構造物の形式が同じならば、大型車両の通行量が多いほど、
劣化損傷は進むということ。
よって、大型車両通過が多い路線ほど、構造物が高級になります。
大型車両の多くは我々の生活に必要な物資を輸送しています。
その物流を維持するためにも、定期的なインフラ点検&維持が必要。
国内道路構造物の多くは高度経済成長期に作られたもの。
すなわち、重交通量にも寄りますが、
一斉に補修すべき時期を迎える。
今、インフラメンテナンスには大きな注目が集まっています。
橋梁を確認する場合、橋の下に降りることも当然!
橋の下というのは、多くの場合河川であって…
比較的水深が浅い場所なら、長靴でなんとかなります。
長靴を履いて川の中へ入っていったわけですが…
じぃ~~んと、内部がヒンヤリしてきた。
ま…まさか…
長靴に穴が開いていたーー!!!
浸水事件です。
こりゃ、帰り道…ちょっと悲しいことになりますな。
その現場が終わり、設楽町内の建設機関に立ち寄って相談事し、帰投。
奥三河をぐるっと一周でした。
このところ、娘が風邪をひいてしまい、
今日は妻が浜松の病院へ連れて行ってくれましたが…
やはり、生後間もないだけに、注意が必要とのこと。
具合が悪くて機嫌が悪いのか、
帰宅後、妻がお風呂に入っている間は私が娘を預かるのが日課なんですが、
今までとは比較にならないボリュームで、ひたすら泣き続ける娘!
しかも、全く泣き止まない。
娘の特徴として、抱っこしながら早歩きしてやると、
落ちついてくるんですが、今日は違う!
全然、泣き止まない。
30分以上、ひたすらテーブルの周りを早歩きで歩き続け、
ようやく大人しくなってきた…。
うむー。治ってくれぇ・・