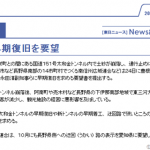日付が変わろうと、花祭りが止まることはありません。
もう、今が何時だったか忘れるくらい、次から次へと舞が奉納されます。

二丁鉾や撥の舞と同じく1人舞の「いちの舞」ですが、1人舞でも舞い方は全く違います。
両手に持った榊の枝葉、ちょっと見えづらいですが、同じく握る鈴と扇。
「本座(ほんざ)」と呼ばれる太鼓の前にある座敷で5方(ごほう:5方向)を舞い、続いて拍子が変わると他の座敷へ移動しながらいちの舞特有の舞でぐるっと一周して戻ってくる。
その後…
鈴と扇を預け、榊の枝葉で観衆を打ち清める!

そこには毎年恒例、これも神様へ奉納する催しなのではないかと勘違いする人が出る!?裸族登場です。しかも、毎年、村内いずれの花祭りにも出没する、「固定」裸族です。
坂宇場花祭りでは、子どもたちが「出番だよ!」と呼びに来るくらい、定着した裸族です。

そして、花祭りの歴史史上初ではないか?といわれる、女性による「いちの舞」が昨年から!!
裸族さんたち、喜んじゃってますねぇ。
このときは支度部屋が何故か?手薄になるため、数枚走り撮りしたのち、私は支度部屋で山見鬼さまの着付けをお手伝い。
昨年の上黒川花祭りで榊鬼を舞った先輩が今年は山見鬼様に。
いわゆる、このブログにもしょっちゅう登場される近所の大っきい先輩であります。

ほんっと、ド迫力!!!!
これぞ!!上黒川花祭りの役鬼。というサイズ感です。
私が仕事で使っている名刺の写真になっています。
その巨大山見鬼さまに対抗してか…。

肩車合戦が始まったようです。
山見鬼さまの大きさに勝つぞーー!!!
ってか(笑)
ちなみに、1月2日のブログでも書きましたとおり、私は次男君を肩車しても山見鬼さまに勝てませんでしたww
その山見鬼さま、ハードな舞を舞った後にもかかわらず。
長女さんが舞う三つ舞のヤチでは太鼓を!

ちなみに、娘さん、まだ肩車してもらっとる。
お父さんがまつりにかかりっきりの中、ミスターいちの舞い裸族くん、有り難う御座います。
そして、私は…

支度部屋へ。
鬼の衣装、着付けに入ります。

独りでは着付けすることができない鬼の衣装。
鬼の親方となると、着付けも入念にして頂きます。
山見鬼さまがいつの間にか、舞台裏写真を撮って送って下さいました☆
あーー。
ドキドキする。
緊張するーーー!!!
鬼を舞っていてい一番ツライのが、焼けるように乾く喉。
ノドの空間がへばりついたように、呼吸が困難になります。
これまでも、梅干しを口に含んでみたり、いろいろ試しましたが…
今回はなんといっても、3ヶ月前から続く咳。
どうにかなっちゃうんじゃないかと。
しかし!!
実は先ほど、山見鬼さまに実験で試して頂きました。
■のど(喉)にヴイックス! | VICKS | 大正製薬
これ。
「調子、良かったぞ!」
というコメントに、私も3粒ほど口に含みまして。
その状態で、いざ!!

出陣。
妻が、素晴らしい写真をたくさん、撮影してくれました。

途中、
「あまり、飛ばしすぎるなよ!」
背中をトンッと叩かれて、同時に力んでいた筋肉から力が解きほぐされました。
そこから自然な舞に集中することができ!
だんだん、楽しくなってきました。

いつもなら、5方睨みで一周するとノドがヤバくなっていたところ、ビックスドロップすげぇ!!
効果てきめんで、喉の渇きや痛みを感じません。
呼吸も、楽です。
ただ、ひとつ、問題があります。
榊鬼では、鬼の舞で唯一、「問答」があります。
面を付けたまま、定められたセリフで「人間」とやりとりするのです。
あめ玉が…。
口の中で緊急避難!!

「我らがことにて候!」
「愛宕山の大天狗、肥後の山の小天狗、山々嶽々をわたる荒御霊…」
言えた、言えた。
そしてすぐ、「へんべい」に入ります。

そして、「かま割り」。

これらの所作は榊鬼特有。
だからこそ、最も緊張する。
上手く行かなかったところもありましたが…。

写真で見ると、バッチリ決まっているように、みえます。

そして、「たい割り」。

今年の松明、めっちゃくちゃ燃えとる。
煙に包まれる舞堂内部。
まだ少しかけらとして残っていたビックスドロップに助けられました。

いやほんと、これ自分?
疑うくらい、カッコイイじゃありませんかー。

面の中では、必死です。

歴代榊鬼様のサポートをいただきながら。

たい割りが終わり、2回目の休憩タイム。
榊鬼が休んでいる間は…
国籍多様な子鬼さんたちによって、個性的な、神秘的空間を作り出してくれました。

休憩を明けてイスから立ち、そのまま「片手マサカリ」。

写真見てみたら、歴代榊鬼様から鋭い視線が飛んできているじゃありませんか。
ドキドキしてきた。
さあ、仕上げ!

本座に戻り、「中」、「天」、「雲」と、マサカリの高さを変えて5方を舞いきり。
これにて終了。

山見鬼さまプレゼンツ、舞台裏写真です。
生きているんか?コイツは?

咳き込んでいます。
生きていますね。

ぶっちゃけ、1年前の花祭りが終わった直後、榊鬼を舞うとなってから、
ずーっと、緊張して日々を過ごしました。
榊鬼って、やはり特別。
花祭りの代名詞は鬼の舞、その鬼の中でも最も難易度が高い。
反省点は多々ありますが、まず、この場に立てたことを喜び。
また来年以降、より良い舞を目指して精進致します。
途中でギブアップにならなくて、本当に良かった。
歴代榊鬼様の諸先輩方、本当にありがとうございました。
そして、大正製薬に感謝申し上げます。
汗びっしょりでぶっ倒れているとき、舞堂では…

これまで私の十八番だった、すりこぎ&しゃもじ、通称「味噌塗り」です。
次男君は、太鼓の音を聞きながらグッスリ就寝中。
良かった、良かった。
味噌塗りに遭遇したら、また中在家花祭りの時のように…。

私の代わりに、すりこぎを「十八番」にしてくれる男が現れました。
今年初めてとは思えないくらい、すりこぎの動きにフィットした生まれ持った才能を発揮したのは…
ミスターいちの舞裸族くん。
豊根村にIターンした、将来有望な若手です。
来年からも、味噌塗りという大役を、よろしくお願いします。

巫女さんが出てきて、婆とのやりとりはいかがだったでしょうか。
続いて、火の禰宜。

写真はありませんが、このあと「翁」も世代交代。
なんと。
ド近眼の翁さんは、面の上からメガネをかけているという…
その風変わりな姿に、笑いをかっさらっていました。
そして私は、会所へ行って念願の…榊鬼の振る舞い酒をゲット!
舞堂の中におられる皆様へ、振る舞って巡りました。
「榊鬼のお酒です。」
と言うと、皆さん飲むにはもうツライ時間(午前5時)にもかかわらず。
飲んで下さいます。
もちろん、運転の有無を確認してから。
東栄町は御園花祭り、東園目花祭りの榊鬼様方にも1杯飲んで頂きました。
一升の日本酒、飲みきって頂けました。
次第は四つ舞へ。

真夜中の熱気から爽やかな朝へ変化する時間帯。

高校三年生の3人、そして豊根村に来て5年目のIターン社会人。
昨年、初めて四つ舞デビューし、見事に舞いきったところ、感心したのも記憶に新しいですが、今年はまた、舞の細かい所作も上達し、幼い頃から花祭りを舞ってきた子たちと遜色ない。

熱意は何物にも代えがたい。
練習は子どもたちの舞が中心なので、ほとんど練習する時間は取られません。
いったい、どこで練習して来たのか??
それは…。
練習の時、ずっと笛を吹きながら刻んでいたステップ、そして観察力。
やっぱり、熱意!パッションですよ!!なにごとも。
誰しも、才能や能力は後から付いてくる。
そしてこの高校三年生たちも、もの凄い熱意を持って花祭りに関わってくれています。

動きがしなやかで、ゆったりと、大きな所作が特徴の上黒川花祭りは、女性の舞にとても合う。

舞えるのが嬉しすぎて、笑顔ですな。

さあ、私は疲れました。
イスに座って目を閉じてしばし休憩…。

していたら、これもまた激写されていました。
今度は奥三河観光協議会のまゆげさんに!!(笑)
皆さん、激写写真の御送付、有り難う御座いますww
四つ舞のヤチ・剣、そして湯囃子へ。
このあたりはもう、手元にカメラがありません。
すみません、写真無しでお送りします。
湯囃子の拍子が変わった途端に目が開きまして!
ひと晩煮立ったお湯を「割」らないと!!!
走ろうとしたら、既に後輩君が段取りしてくれていました。
これぞ、花祭り。
役割分担を特に決めているわけじゃありません。
気付いた人、誰かがやる。
湯囃子メンバー、今年は大入れ替えしています。
ってか!!!!
湯囃子の太鼓、山見鬼さまが叩いている!!
なんという、恐るべき体力。
ちなみに、太鼓も誰が何を叩くかあらかじめ決まってはおりません。
その時々、叩けるひとが叩く。
そして…!!!
湯がほとばしり!!
びしょ濡れになりながら、釜に湯(もしくは水)を継ぎ足し続ける私と後輩君。
水道水の流速が負けてきて、焦ります。
外からも汲み入れて。
キンッキンに冷えた水を。
湯囃子、賑やかに幕を閉じました。
舞堂へおがくずを敷き詰め、土間の水分を取り去ったところで朝鬼様登場。
いやはや、カメラ、全く持っておりませんので写真が無くて申し訳ありませんが…。
またまた、奥三河観光協議会のまゆげさんが送ってくれました。

びしょ濡れになって休憩中の朝鬼さまを仰ぐ姿を。
年季の入った、大先輩の朝鬼様、有り難く拝ませて頂きました。
完全に明け切った朝。

獅子舞の拍子を聞きながら、これで今年の上黒川花祭りも終わったなぁと。
なんともいえない疲労感、誰しも顔に浮かんでいます。
しめおろしで注連縄が切られ、本当のフィナーレ。
氏子総代長から全員に向けて、感動のご挨拶。
身に染みます。
その後も、ホコリまみれになりながら後片付けを、これもまた、担い手がみんなでやるべき事をそれぞれに見つけながら。
午前11時、後片付けも終了しました。
最後まで残っていた長男とともにパルとよねで湯船に浸かり。
帰宅すると…。

おい。
花祭りが始まっている。
調子に乗って笛を吹いてやると…驚いたのが、笛の拍子の違いを意識して太鼓の叩き方を変える次男君。2拍子の太鼓をたたけているじゃありませんか。
耳コピですな。
まだ、しばらく我が家は花祭りが続きそうです。
仮眠を3時間ほど取りまして。

久しぶりに来ました!!
とみやま地区の御神楽まつり!!
30時間の徹夜後、3時間の仮眠を経てまた祭りとか、
狂気の沙汰と思われても致し方ありませんな。
今年は、休日の相性がすこぶる良いのです。
まだ、明日、1日お休みがある!
そう思ったら、行くしかありません。
花祭りのうたぐらに、
「嶺は雪、麓は霰、里は雨」
とあります。
そのうたのとおり、自宅周辺は雨降りだったのが、三沢にさしかかると霰になり、霧石峠は雪でした。
霧石峠から下って、富山地区まで行くと雨に。
日頃お世話になっている富山地区の皆様に御挨拶し、団長さん、副団長さんもおみえの消防団夜警にもお邪魔させて頂き。
御神楽まつりを楽しみます。
面の舞が始まりました。

「どんずく」の獅子さんに、続々とミカンが。

たらふくみかんを頬張ると、一旦休憩しながら…みかんを消化中!?

ここで次男君。

大泣きです。
まるで、味噌塗りに遭遇してしまったかのような大泣きです。
どんずくより注目を浴びてしまい、肩車をしながら一目散に逃げるお父さんです。
鬼神の面に続き、兄弟鬼が待ち受けます。

マサカリの扱いが上手いなぁと思いながら兄弟鬼の舞に見入る。

そして…おもむろにマサカリの刃を研ぎ始める。

ひとつひとつの所作が面白い。
それに対する周りからの「野次」も、面白い。

榊の葉を手に持ち、研ぐ!刃を研ぐ!

続いて、「禰宜」

有り難く、お祓いをして頂いたかと思ったら…
奥の方からひょうきんな声が聞こえて来た。
「ホーッ!ホロロゥー!」
文字に起こすのが難しい音声です。
かと思えば、

華麗な跳躍!!

「はなうり」さまやー!
この跳躍力、きっと彼ですな。
そして動きが滑稽な「しらみふくい」さま。

筋肉隆々。

数々の個性的な面が登場し尽くし、最後に
「ごじんごー!」

見物人へ、有り難いおこわをくださいます。

次男君も、頂いて大喜び。
しめきりにより結界が解き放たれて、空間は日常へ戻る。

花祭りでいう「しめおろし」。
距離は近くとも、山を隔てると全く形の違う祭りが営まれている。
伝統芸能は、本当に面白い。
しかし、担い手は減少の一途。
いつまで続けられるか。
昔は祭りの楽しみというのは、唯一の娯楽だった。
そんな時代と違い、娯楽の溢れたこの世の中において古い芸能が残っていくには…
やはり、熱意か。
お金があれば続けられるわけではありません。
お金は必要条件であり、十分条件ではありません。
祭りのために日常生活を犠牲にしちゃうくらいの熱意…か!?
また、伝統は必ずしも守るべきものではなく、変わることが当たり前であり、変わってきたからこそこれまで続いてきていると、かつてお目に掛かった人間国宝の方がおっしゃっていました。
まさに。
思い馳せながら、帰り道、白く雪化粧された霧石峠を越えて帰途に就きました。
もちろん、午前様ですがな。
帰り道、運転有り難う、妻よ。