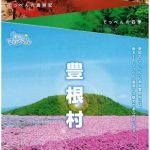勝てば官軍、負ければ賊軍のごとく、歴史は強者によって編纂されるのは世の常。
国盗りを制した一族によって、過去の歴史は後世に残されていきます。
すなわち、国盗りに敗れた一族の歴史は、後世に引き継がれていかない=葬り去られる。
歴史に詳しいわけではありませんが、古代から始まって現代にいたるまで、歴史の授業はいつも政治の中枢ばかりです。
例にもれず、日本最古の歴史書である古事記も。
大和朝廷が世の中をおさめるための道具として編纂されました。
『古事記』は歴史書であるとともに文学的な価値も非常に高く評価され、また日本神話を伝える神典の一つとして、神道を中心に日本の宗教文化・精神文化に多大な影響を与えている。『古事記』に現れる神々は、現在では多くの神社で祭神として祀られている[注釈 2]。一方文化的な側面は日本書紀よりも強く、創作物や伝承等で度々引用されるなど、世間一般への日本神話の浸透に大きな影響を与えている。
ただ、神社が好きならば、一度は目を通したい歴史書。
古事記は上中下巻からなり、上巻の「神代の巻」は天地創造から天照大御神など様々な神様にまつわる話が展開され、中下巻の「人代の巻」には初代神武天皇から推古天皇(第33代、592~628年在位)までの歴代天皇の系譜などが記されています。
そこには、八百万の神々の名前が。
上巻で登場する主な神様は次の通り。ウィキペディアより。
全国津々浦々の神社で祀られている神様の名前が、ここにいくつも登場します。
特に、島根県の出雲が舞台として数多く登場します。
また、宮崎県の高千穂も。
大和朝廷が天皇を中心とした権威づけをするために編纂された書物なので、神話に乗せられた当時の力関係がここから垣間見えます。例えば、出雲地方は当時、大和朝廷の脅威となるほどの、強力な豪族(裕福な土地)があったことが推測されます。
また、神社などで祈祷してもらうときに神主さんが詠まれる祓詞には
「筑紫(つくし)の 日向(ひむか)の 橘(たちばな)の 小門(おど)の 阿波岐原」
というフレーズが入っています。
皆さんも祈祷してもらったとき、聞き覚えがあるのではないでしょうか。
これは、場所を示しているんですね。
どこにあるのか調べてみました。
古くは今の大塚地区と下北方地区との間の三角州、すなわち旧宮崎市街地全域を小戸と称し、「筑紫の日向の橘の小戸」の地名そのままに太古伊弉諾大神が禊祓をされた“祓の神事”由縁の地であり、天照皇大神をはじめ諸貴神誕生の聖地神社である。
宮崎県!!この地こそ、神武天皇がお住まいになっていた場所。
ここから、東へ向かう東征が始まり、大和を平定します。
高千穂の神楽、ともども、九州へ行くことがあったら立ち寄ってみたいと思います。
いろいろと、祓ってもらわないと。
古事記の現代訳をチラッと見てみたい方は、こちらのサイトがおすすめ。
古事記など、日本神話は神様がたくさん出てきすぎて、読んでいて訳が分からなくなります。
特にその、血縁関係。
神様の男女から新しい神様が生まれることもあれば、神様が身に着けている道具や体の一部から生まれることもあって、系図を整理しながら読まないと。
わかりやすい系図をネット上でまとめている方がいらっしゃいます。
神話の世界と現世天皇陛下の系図がリンクする「上つ巻」。
なんでこんな記事を書いているのかというと…
最近読んだ、こちらの本。
とってもわかりやすく、神話の世界と、当時の歴史や政治の世界をリンクして書かれています。
神社が好きで巡っているけれど、そのたびに遭遇する「祭神」の名前。
その御祭神が神話の世界でどういった位置づけになっているのか、知って巡ると、また違った趣が味わえること間違いなし。
記紀(古事記、日本書紀)が中央政府の公式の歴史であるのに対し、「風土記」は地方の公式記録の性格を持つ。「出雲国風土記」「常陸国風土記」「豊後国風土記」「肥前国風土記」「播磨国風土記」などがある。このうち完全な形で残されているのは「出雲国風土記」だけ。
天神は伊勢系の神、国神は出雲系の神。天神は大和朝廷の奉祭するアマテラスをはじめとする支配階級の神であり、地神はそれに服従した支配階級、すなわち各地の豪族が奉祭した神である。戦国時代ごろから、国神は妻入(屋根が三角の方から入る:出雲大社)にまつり、天神は平入(屋根が水平に見えるほうから入る:伊勢神宮)に祀るという公式が出来上がった。
出雲大社の宮司は天孫のアメノホヒの末裔とされ、宮司職は出雲の国造(今の県知事に相当)が代々世襲して務める。現在まで宮司家の千家家は84代、1300年以上続き、日本で最も長く続いている由緒正しい家系である。
ここに引用したのは一例ですが、伊勢系と出雲系、また出雲大社の歴史ある宮司職など、興味深く初めて知る知見がたくさんちりばめられています。