橋梁研修、2日目になりました。
今日は、ひたすら…
鋼部材とコンクリート特集です(笑)
まさに、材料力学。
大学時代に学んで、ようやく役に立つ日がやってきました。
勉強していて、無駄になることなんて、やっぱり無いんですね。
意外なところで、役に立つ。
朝早く到着しすぎて、講義室一番乗りでした。
続々到着する受講生、そして話題は…
昨夜のNHKニュース。
昨夜遅くに、豊橋の伯父さんからメールが来て、
どうやら私もチラッと映っていたらしい!
8時45分のニュースでも流れていたんですね。
観てみたいなぁ~と思っていたら、
前の席の方が、ネットでも配信されてたよ!と教えてくれました。
橋の老朽化対策で自治体研修会 – NHK 東海 NEWS WEB
この研修会は、おととしの道路法の改正で、すべての橋やトンネルの5年ごとの点検が義務づけられたことを受けて、自治体の職員に点検に関する知識を持ってもらおうと、国土交通省中部地方整備局が初めて開き、初日の26日は、愛知・岐阜・三重を含む5つの県の自治体の担当者44人が参加しました。
昨日はあまり詳しく書きませんでしたが、
情報がオープンになっていたので、ご紹介。
国土交通省の中部地方整備局さん主催。
法律改正で必須となった道路橋の点検。
今回の研修会は4日間の日程で行われ、整備局では、小規模な橋は、自治体職員だけで点検できる程度の知識と技術を身につけてもらいたいとしています。
できるだけ、村の出費を抑えるためには、
自分たちで自ら点検する能力を身につけること!!
大きい自治体には、専属で専門職の人がいるので、それが可能ですが、
やはり、小さな自治体には、難しい問題。
専門的な知識が求められます。
その専門的な知識を研修を通じて学び取り、
小規模な橋ならば自分たちで点検できるように!
はい、がんばります。
点検業務を外注したとしても、
発注者が責任持って成果品を判断できなければなりません。
いずれにせよ、知識は必要。
そういった専門的な知識が4日間に凝縮されて、
濃密な研修となっております。
更に配布されたプリントが増えまして…
厚さ20センチが近づこうとしております。
しんしんと降り積もる雪のように…。
恐ろしい情報量。
講義のスピードも、その情報量を処理していくので、なかなかの速度。
はい、がんばります。
1日を終えて、初めて聞いた用語がたくさんで頭がいっぱい。
頭を抱えながら、地下鉄に乗って向かったのは…名古屋大学。
2012年の4月に私たちがサウジアラビアへ渡航したとき、
現地で我ら青年交流団の通訳をしてくれた方。
サウジアラビアにて、日本語を巧みに操り、
アラビア語を翻訳し、また伝えてくれました。
まだ若くて、20代!
彼は、とても勉強熱心だった記憶があります。
通訳をしながら、分からない日本語があると、我々から日本語を学び取ろうとしていました。
なんの偶然か、彼は昨年から名古屋大学に留学中!
日本語を更に深く、勉強中なのです。
中央図書館の入口で待ち合わせにしておりましたが、
まだ集合まで時間があったので構内をフラフラと。
文学部の前を通りかかったところで…
車に荷物を積み込んでいる二人組さんから、
なんだか聞き覚えのあるような声が…。
周囲は暗闇だったので、その横を通り過ぎつつ見たことのあるシルエット。
よーっく顔を見てみたら…
名古屋大学の花祭りお兄さんたちじゃありませんか!!!
今年の上黒川花祭りにも来て下さいました。
お兄さんたちが現れると舞庭の日本酒が消滅するという噂の…(笑)
「あ!す○さん!」
声をかけましたらば、お兄さん、かなり驚かれるww
「なんでここにおるのーーー???」
続いて一言。
「これから、豊根行くんだけど、乗ってく?」
って(笑)
今から出発ですか!
しばらくまた、花祭りのリサーチを北設でやるそうです。
乗っていくのはとっても楽しそうなんですが、
明日もまだ名古屋ですので!
サウジフレンドとの待ち合わせの時間まで、
一緒に待ってて下さる優しさ。
コーヒーごちそうさまでした。
そして待ち合わせの時間となり、お兄さんたちも一緒に連れて行っちゃいました。
何か、化学反応が起きると面白いなぁ~って。
案の定、さすがはアフリカ文化に造詣の深いお兄さん。
サウジの彼と言語の話が始まりました。
そこにいる4人の共通点は、この大学。
いろんな繋がりを作ってくれたこの大学に感謝。
つかの間ではありましたが、豊根に向かうお兄さんたちを見送って、
我々は近くのレストランへ行き夕食を一緒に。
まず、席に着席してから、積もる話がありすぎて、
注文するのをすっかり忘れるふたり(笑)
留学生にありがちなんですが、
学校と自宅の往復で、日本人と普通に喋る機会が少ない。
これが悩みの種のようです。
いつも豊根に来る留学生さんたちも、そう言っていて、
豊根に来ることで、日本語を試すことが出来る…と、喜んでいる人もいます。
悩みのダムが決壊したように、マシンガントークでした。
もう3年近く前になるんですね。
サウジアラビアで出会った日は。
思い出話にも花が咲きました。
そして、今やアラブ世界で有名な日本人となった、
我ら青年団メンバーのあの方の話で盛り上がりました(笑)
帰り際、せっかくだから、ふたりの母校で再会を果たした記念に写真を撮ろう。
いやしかし、誰かに撮ってもらわないと…背景が映らない。
警備員さんがいたので、頼んでみたら、見事に断られ…。
ですよね。業務中ですもんね(汗
数少ない通行人の方を引き留めて、シャッターをお願いしました。

固い握手と共に、彼が修士課程を卒業するまでに、また何度か会おう!
そう約束して、散会しました。
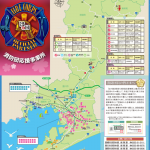



見ました!
隣の方は大あくびしてましたね^^
別の場所に書き込ませていただいた「再生式受信機」の件ですが・・
子どもの頃、我が家のラジオも再生式でした。
高周波増幅回路が1段付いた4球ラジオで、「高1」と呼ばれました。
再生バリコンのツマミを回し、発振寸前で止めるのですが、これがなかなか難しくて。
すぐに発振し、ピー、ギャーとすさまじい音を響かせます。
影響は、近所のラジオにも及ぶのです。
戦後、進駐軍が電波障害の酷さに驚き、再生式ラジオの生産を禁止しました。
メーカー製はすべてスーパーヘテロダインになりましたが、わしらラジオ少年は相変わらずピー、ギャーの世界でした。
鉱石ラジオから始め、3球式の「並3」、低周波増幅管をプラスした4球式の「並4」と進むのが普通のコースでした。
なぜ「並3」とか「並4」と呼んだのかはわかりません。
スーパーが「上」で、再生式は「並」だったからでしょうか。
同じ4球式でも、高周波増幅回路付きは「高1」でした。
あのころ、ハムが多用していた高周波増幅1段、中間周波増幅2段の受信機は「高1中2」と言ってました。
お金がなくて手が出なかった高1中2、数年前にトリオの中古を3機種入手しました。いずれレストアするつもりです。
>山のしんぶんやさま
ご覧になりましたか!
大あくび(汗
まあ、人それぞれ…興味のツボというものがあるんでしょうか…ね(汗
電波の歴史と同じような歩み方を、少年が成長すると共に歩んでいく…
そんなイメージでしょうか。
「上」とか「並」とか、まるで牛丼、鰻丼のような…ww
進駐軍も、個人が作成している受信機までは目を光らせていなかったんでしょうかね。
近所のラジオにまで混線するとなると、電波Gメンが…!?
レストアも御自身で実施されるんでしょうか!
どんな風にレストアできるのか分かりませんが、
まだ「見て分かる」回路なら…できるんでしょうかね。
レストアする暇が無いくらい、良いニュースが北設を飛び交うと良いのですがww