様々な判断をしながら生きる上で、
自らの思考回路が通り一辺倒であるほど判断を誤りやすく、
回路の中に全く違う方向を向いている回線があること…
すなわち。
頭の中にいろんな種類の回線が共存した回路であること。
判断をするときは、いずれの回線にも通電させてみること。
これこそ、生きる上での判断を見誤らないことと思います。
その意味で、この書籍が綴る孤独の概念は、また新たな回線を構築するべく、
頭に入れておいたら人生の参考になりそうです。
執筆者の森博嗣先生といえば、「すべてがFになる」や「スカイ・クロラ」など、
ミステリー作家として非常に…ひじょーーーに、有名な方。
そのミステリー作品は、読み始めると読破するまで取り憑かれたような魅力満載。
特に理系人間が読むと、クスッとしてしまう工夫が随所に。
2005年に退官されるまで、名古屋大学工学部の助教授でいらっしゃり。
教養課程の授業だったかと思いますが、少しだけ御講義を拝聴したことがあり。
学内でフラッとすれ違うこともあって、
心の中で「おおおおおー!」と思った記憶があります。
武田研究室に入ってからは、
森博嗣先生が隣の建物だったこともあり…
道端での遭遇率も高かった。
(さすがに、恐れ多くて声をかけられません。)
表題の通り、「孤独」状態が持つ価値をテーマに、
現代人は「繋がり」という「鎖」に縛られ、商業主義による感動支配。
感動支配がそのまま、人間の生育に影響を与えた結果…。
子育てする上でも、親として何を考えるべきか。
その答えが載っているわけではありませんが、
気をつけるべきだなぁと感じることは多々あります。
例えば、子どもたちが楽しく見ているテレビ番組について。
多くのエンタテインメントでは、仲間の大切さを誇大に扱う傾向があるし、またそれに伴って、孤独が非常に苦しいものだという感覚を、受け手に植えつけているように観察される。
仲間と一緒に感動的な結末を迎えて、感情が動かされる人が多くなれば、
仲間を大切にする作品を作れば売れる。
感動というのは、商売にとって非常に重要なファクター。
感動しやすい視聴者を「作り上げれば」商業的にも成功する。
感動のスポットとして、仲間の大切さを扱うことは王道的。
より販売数を上げるために、仲間の大切さを肯定的に洗脳する。
一方で、孤独やさみしさをテーマにして、
万人受けするエンターテインメントって…思い当たりません。
かなり、天邪鬼的発想ですが!
論理的破綻はありません。
「孤独」という文字列に対して、孤独死や孤独=オタクなどとして、
孤独という言葉は、「寂しい」と、否定的に使われることが多いですが、
一人でいることは寂しいこと、寂しいことは悪いこと、という処理を、考えもしないでしているだけなのだ。同じ価値観で返せば、そういう「考えなし」こそが、人間として最も寂しいのではないか
「孤独=悪」と、決めつけちゃダメだよと。
「孤独」について、肯定的に書いてみたら、それもストンと腑に落ちる。
ものを発想する、創作するという作業はあくまでも個人的な活動であって、
それには、「孤独」が絶対に必要であるということ。
わいわいがやがやとやっている時間から生まれるものもゼロではないが、そんな例外は、一人のときに悩み考えていた人が、その賑やかな場のリラクゼーションからふと思いつくアイデアである。
創造性の必要な仕事を進めるとき、
必ず、ひとりで孤独に考える時間が必要。
(創造性が必要無い仕事なんて、存在しないと思います。)
ブレインストーミングでアイディアを出し合っているのも、
結局は、ひとりひとりが孤独の時間で考えたことが脳内に蓄積されていて、
ブレストの場でオープンになる。
ひとりひとりの蓄積が無ければ、効果的なフレーズは誰からも出てこないでしょう。
ちょっと話は飛びますが、自らがその瞬間に抱いている感情によって、
周りから入ってくる情報のとらえ方が180度替わるってのは、良くあることです。
自分が抱く感情というのも、実は瞬間ではなくて…
人間は、現在の状態ではなく、現在向かっている方向、その「勢い」によって感情を支配されている場合が多い。
とのこと。
なるほどなぁ。
この文章について、数学でいう「微分」と示され、
三角関数を引用しているのが面白いです。
人間の感情は、変化量「デルタΔ」によって決まる。
とおっしゃっていた武田先生に通ずるモノがあります。
また、子育てのみならず、地域活性化に取り組んでいる我々としては、
それらが否定されたような気分になる場面もある。
穿った見方をすると、地域活性化や地域創生というのが、
商業主義の仲間入りをし始めたようにも感じる。
この本を読んでみて、
なんだこれは?全く理解が出来ない。
そう思われる方は、己の考え方に自信がありすぎるのかもしれません。
嗜好に合わない本は、いくらでも出会ったことがあるけれど、
それぞれに対して批判的に読書を進めると読書の意味が無い。
どちらかといえば、私も、「孤独」に対しては否定的なスタンス。
自分の考え方に、変化がありました。
嗜好に合わない本があるからこそ、読書は面白い。
そんな本に出会ったときは、ヨッシャ!と思って、
先入観を捨てて、いかに著者の言うことを肯定的に読み進められるか。
それが重要。
ものごとは中庸。
傾いていないつもりでいても、
実は傾いていたと気付くことが出来るのは、真逆の思考を取り込んだときのみ。
思考を中庸により戻す良い薬。
だまされたと思って、読んでみて下さい(笑)
本書の理解に苦しんだら、「あとがき」必読です。
孤独とほとんど縁のない人にとっては一読の価値ありですが、
既に本書のような孤独の世界を邁進している方が読んだ場合、
自分を正当化してしまう危うさがあります。
この本を通して、多様な価値観の一部を受容できるようになるかも。


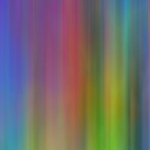

最近、よく感じることは…、孤独に耐えられない人(子ども)が増えている…。
私は、
「たとえ今ひとりぼっち(孤独)であっても、自分が楽しい、やりたい、やりがいを感じると思うことをし続ければ、必ずそこに集まってくる人がいる」
と考えています。
なので、友達関係で悩んでいる子どもに出会うと、いつもこう言います。
「孤独に耐えることも学びなさい。」
と。
でも、難しいみたいですね…。どうしても安易に繋がれる人を友達として、流されていってしまう…。
まあ、詳しく書き始めると長くなりそうなので、いつか機会があればごゆっくりお話しします。
教育現場での所感、ありがとうございます。
テレビなどのメディアから洪水のように「仲間」や「絆」を強調されると、
そうしないことが悪であるかのように感じてしまうのも無理はない気がします。
特に、吸収力の高い子どもたちならば。
まさにおっしゃるとおりで、孤独のうちであろうと、続けていくことで自然に人は集まってくる。
自分が孤独に感じていても、周囲は見ています。
そして、それを推し進めるためには孤独に耐えることも!
また、星空眺めながらお話ししましょう(笑)
森博嗣さんと言えば第1回メフィスト賞作家、「すべてがFになる」は「那古野(なごの)大学」が出てきたり、物語の舞台が三河湾の島のようだったりと愛知県ゆかりの方らしいですね。
メフィスト賞作家はかなり読んでいるのですが、最近同賞出身作家の古野まほろ氏が豊橋出身らしいのをご自身のTwitter@で知りました。森さん以上の覆面作家なのです。
覆面作家の方の覆面が剥がれたときはドキドキしますね(笑)
自分の知っている情景が描写されるとより興奮しながら読書が進みますww
読書の秋!花祭りの冬!
睡眠時間が激減しそうです(汗