4月に異動してから、きっと出張は無いだろうと思っていたら…あった。
医療分野においても、企画&デザインする仕事があることを知り。
知るどころか、とても大切な仕事だということがわかり。
それもまた、高齢化が急速に進む日本においては、待ったなしの仕事である。
早く方策を立案するべく、情報収集&知識導入を手っ取り早く済ませるためには研修が一番。
それも、第一線の、制度設計をしている国のセクションから話を聞くことができる貴重な機会。
この日に照準を合わせて仕事を整え、早朝、職場を出発。
本社の同僚、出先機関の同僚、そして村の福祉機関の方とともに。
向かった先は名古屋市公会堂。

鶴舞には、武田先生の会でしょっちゅう来ておりますが、公会堂は久しぶりです。
昭和5年に開館した、歴史ある重厚な建物。
その上層階にあるホールで、東海三県の担当者が勢揃い。
なにをここで考えるのかというと…
団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。
今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
4月に入って、初めて耳にした言葉、「地域包括ケアシステム」。
地域包括ケアシステムというのは上記、厚生労働省の紹介文の通り、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムのことを言い、これを構築することが喫緊の課題となっています。
内容としては、医療分野に限るものではなく、行政で言えば全ての分野に通じる、地域デザイン的なシステム構築が理想とされており、地域づくりや企画、地域振興的な視線が重要になります。
よって、国が決めたルールに従って事業を構築して進めるというよりも、市町村がそれぞれに、それぞれの地域に適したシステムの形を模索して組み立てるものになります。
そのための情報提供を国は多々行っており、Web上にも情報が集められています。
■地域包括ケア市町村セミナー
■市町村等職員初任者セミナー(2018年6月7,11日開催)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000114064_15.pdf
今の時代、会議資料がネットに公開されているんですね。
今回行ってきた会議の内容、昨年のものが公開されています。
そして、主体となっているコンサルタント会社からは調査研究レポートが多々公開されています。
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた制度やサービスについての調査研究 【報告書】
流行というか、自ずと向かっているというか、土木分野も医療分野も、観光分野も。
いずれの分野においても、近年においては地域マネジメントを抜きに語ることができない時代です。
■地域マネジメント | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_05/houkatsu_05_3_honpen.pdf
このシステムを作るためには、先行事例を学ぶことも大切。
なかば、自分のメモ書きのような記事になりましたが、参照しながら豊根村における最適モデルは何なのか?現場で調べながら作りたいと思います。つっても、待ったなしだから、ノンビリ構えていられませんが(汗



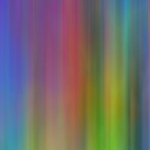
「名古屋市公会堂へ、地域包括ケアシステムについて学ぶ」への1件の返信