昔働いていた会社は、人事マネジメントシステムがきっちりしていたなぁと、今振り返ってみると思うわけですが、システムはシステムで、結局決めるのは管理する「人間」です。
システムと人間。
どちらか一方だけがしっかりしているだけでは、機能しないのが人事。
と、個人的には考えているわけですが、今働いている業界では、組織によっては「人事が全て」のように考えられていることも多々あります。
我が社は、良い意味で、そうでもありませんが(笑)
同じ業界他社で、面白い人事マネジメントシステムを構築している組織がありました。
たまに訪問して知識を仕入れさせてもらっているサイトから。
■【元豊田市 伴幸俊 #3】人事制度改革のメリットとデメリット – Heroes of Local Government
役所の仕事を、4系統17分類。
通常ですと、過去に携わった「課」のみが職員の履歴として残っていくわけですが、「課」という分野の分類だけではなく、それが企画なのか、住民対応なのか、管理なのか、そういった行った業務の履歴も踏まえてローテーションさせるという仕組み。ただ課を動かすことだけが異動ではないという概念。
35歳までは自分自身のやりたいことを見つけてもらうようにしています。それから、スペシャリスト系でいくのか、ジェネラリスト系でいろんな部署を渡るのかは個人が選択できるようにしています。
質の高いサービスを提供するには、専門性は欠かせません。自治体の職員がそれなりの力を身につけなければいけないと思います。もちろん、部署をある程度固定したからといって、本当に素晴らしい仕事ができるようになる保証はありません。癒着のような心配もある。それでも、行政が専門知識を求められている時代です。優れた政策を立案できるスペシャリストをもっと育てるべきだと思います。
なにも、優れた政策を立案するのは企画セクションの専売特許ではありません。
現場で住民に身近な場所で仕事をしていないと立案できない企画だってあります。
だからこそ、全ての職員が企画能力を持つことが大切。
その意味でのジョブローテーションは必要ですね。
特に、小規模な自治体で働いていたら、ひとりも漏らさず、全ての職員が優れた企画能力を持つ必要があります。その力を磨いてもらうために、マネージャーはなにをすれば良いのか。って考えるのはマネージャーに課せられた至上命題だと思っています。
それができなくなった組織はきっと…。
マネージャーが企画するよりも、部下に企画させるように仕向けること。
話が逸れました。
そもそも、異動を繰り返して色んな部署の制度を知れば、立派な公務員になれるという勘違いはありますよね。単に制度を知っても、それを正しく使いこなし成果にコミットしなければ、知らないのと一緒です。
・・・異動と関係なく、与えられた現場で自分なりの目標を立て行動に結び付けている。そして、日々勉強と行動を繰り返して成果を出す。そうした職員が今注目されているのではないかと思います。
まさに、これ。
異動先で単に制度を知るだけじゃあ、知らないのと一緒。
どこに異動しようとも、自分なりの目標を立てて行動していき、それが運良く成果に繋がれば。
それを皆ができるようになったらもの凄い強い組織になります。
また、別の記事ですが、豊田市では上司診断たるものが導入されていると。
■【元豊田市 伴幸俊 #2】組合員による上司診断の導入が、人事改革の布石 – Heroes of Local Government
上司診断というのは、部下が上司を評価する仕組みです。評価項目として、「指導力」「企画力」「調整力」などを部下が点をつけるのです。漠然と指導力で何点とつけていくのではなく、「課員の前で課の今年の方針を説明しているか」など具体的な行動として部下に評価してもらいます。これなら部下も評価できますし、評価される側の行動指針にもなります。自己評価もありますので、「これをやれてなかったなあ」という反省材料になるということです。
また、上司診断の結果を人事考課に反映する市もありますが、豊田市では部下からの人気取りになることを防ぐために、人事考課には入れませんでした。部下は上司を正しく評価できるとは限らず、「いい人だな」とか、そんな程度のことで評価されたものが、昇任や昇給、あるいはボーナスに影響するのは違うかなと思ったからです。
上役に立つ人たちもリスクを持ち、ある種、ヒヤヒヤしているという。
ただ、人事考課に入れていないというのも、人間という生き物を分かっていらっしゃる。
もうひとつ、漠然と、私も思っていたことが文字になっていて、改めて「そのとおり!!」と思った記載がこちら。
よく「人材育成はどうしていますか?」と自治体の人事担当者に聞くと、「研修をやっています」って返事が来る。でも、私は研修で人が育つというのは真っ赤なウソなんじゃないかと思っています。
もちろん、自己啓発の動機づけにはなりますが、研修で人が育ったなんて実感したことは少ないです。
そう。
研修はあくまで、自己に対する動機づけに過ぎず、研修を経て新しい知識や世界を少しでも垣間見たら、それを自ら調べて、学んで、研鑽して、実務で試して。そうして始めて、研修した意味があるというもの。
ただ「行ってきましたー」っていう研修が、あまりにも多すぎる。
研修に行ってきた報告書を書いておしまい?そんなのは論外です。
そんなモチベーションで研修に行くくらいなら、その時間を使って住民のために問題解決のひとつやふたつを進めたほうが学びとなります。
ちょっと、引用しすぎかもしれませんが、最後に、この文面だけはしっかり目に焼き付けて。
加藤:長い公務員生活の中、仕事をするうえで、日々どのような点を意識されていましたか。
伴氏:与えられた仕事に対して自分流のスタンスを固め取り組みます。常に「何か変えるべきことはないか」という意識を持ち、現場での課題を見つけてそれを解決していく。これを続けるだけです。政策や対処の方向を迷ったら「これをやれば必ず市民が喜ぶ」という判断基準を意識し続けます。組織の都合や我欲に陥らない判断をすることは簡単なようですが、流されることも多いものだと思っています。
役所の中では「市民目線で行こう」って言う人は沢山いるんだけど、最後の最後まで市民目線で仕事している人は少ないと思います。困った時は、内部を意識する。予算がない、人がいない、難しい、忙しいとか、いろんな都合で「今はやらない」と結論づける。
その意識をできるだけ市民に向けて、市民の感覚だったら何を求めるのかを、最後の最後まで意識して、今必要な仕事を判断していくことが大切だと思っています。各地域によって、職場の風土も違うし、地域のかかえる課題も違う。目指すべき経営方針も違う。従って人事制度にはこれをやれば100点なんてものもないと思います。
さすが、トヨタのお膝元。
なんだか、考え方の至るところにトヨタイズムが。
現場で課題を見つけて解決すること、その課題解決はお客さまのため、お客様第一。
一人ひとりが高い品質を作り込むこと。
それは民間の専売特許じゃありません。
お役所だって、もちろん、必要なこと。
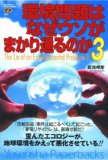



Exactly
記事を読んで、共感すること多々ありました。
誰かに反応して欲しかった記事、さすが、期待通りの方に御反応頂いてうれしや!です(^_^)ゞ