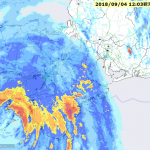1月3日から4日にかけて夜通し行われる上黒川花祭り。
4日に日付が変わってから…の、続きです。
そのころ、私は赤い衣装に身を包み…
口の渇きを抑えるため、梅干しを口に頬張り。
出番を待ちます。
そして、出陣の合図。

今年もまた、山見鬼を拝命。
大変ではありますが、光栄なことです。

傍らでは、山内の榊鬼様が熱視線を送っておられます。
知っていたら、更に緊張していた…。
重たい面を付け、真っ暗闇に閉ざされた視界の中で、微かな光と音を頼りに…激しい舞を舞う。
榊鬼様に比べたらまだ楽な方でありますが、それでも…しんどい。
やはり、いざ舞庭に出るとだらけた舞をすることはできませんし、自分が間違えやしないかと緊張してしまいます。
この緊張が大敵。
「力が入りすぎだぞーー!」
先輩から檄が飛びます。
はいっちゃうんだもんー。
しかし、先輩がおっしゃるとおり。
初っぱなから飛ばしすぎて、まだ半分も過ぎないところで、呼吸がキツくなってきました。
睨みながら釜の周りを一周し、最初の休憩になり。
イスに座って呼吸を整えようとしたら、過呼吸に(汗
完全に、酸欠状態。
今すぐにでも面を外して新鮮な空気を取り込みたい衝動に駆られつつ、グッと堪えて。
毎年、毎年が、新たに知ることがあります。
鼻呼吸だけじゃダメだ。
梅干しも、善し悪し。
ただ、喉が渇かなかったのは助かった!!
お父さんの様子を収めようと、深夜にもかかわらずビデオカメラを回す長男氏。

いつか、その撮影した動画を見ながら、彼も鬼の面をかぶる日を夢見て。
口の中に滞在させておいた酸味ほとばしる梅干しをグイッとのみ込み、口呼吸を併用。
そうしたら、随分呼吸が楽になった。
最後まで舞いきったときは気持ちよい疲労感とともに、まだまだ反省すべき点が多々ある曇った気持ちが共存。
「山見鬼の清酒」を受け取ったところで、ようやく、山見鬼を舞ったんだなぁと実感しました。
清酒と茶碗を手に持ち、着付けなどの支度をして下さった方々、太鼓を叩いて下さった方、お世話になった方々から酒を注いで回ります。さらに、会場にいらっしゃる方々へも振る舞いながら巡り。
その間も舞式は続き、三つ舞のヤチ。

上黒川花祭りにおいては、太鼓の音色を止めてはならないという暗黙の了解があります。
次の舞に移るとき、多くの場合は太鼓のたたき手もチェンジしますが、その際、太鼓を叩きながらのチェンジ。
このような所作は他所の花祭りではあまり見ません。
一度、音のない空間が現れてから、再び音色を奏でるところがほとんど。
上黒川花祭りでは、連続性が重視されています。
まるで、一晩中続けられる舞を統べて一つの舞としているかのように感じます。
今年は山内花祭りから応援団が!?
観衆と舞が一体となった姿がここに!?

次第は三つ舞の剣へと。

年末に負傷して、ほとんど練習できなかったにもかかわらず、勇壮な舞を。
ここで、太鼓のたたき手がしばらく連続してしまっているという情報が。
この時間帯から、太鼓のたたき手も疲労がたまり、また不足してきます。
舞の途中ではありますが、様子を見ながらバトンタッチしました。
本番で叩くのは初めての舞。
ま、途中までではありますが、先輩の休養になれば…と。
そして!!!
いらっしゃいました!!!
榊鬼様。

上黒川花祭り史上、最大の榊鬼様です。
それを示すかのように、長さが足りなくなった榊鬼様のマサカリは…
長さが延長されています。
山見鬼と対称的サイズ。
山見鬼の舞に、更に「問答」、「釜割り」、「たい割り」がプラスされ、非常に過酷な舞。
特に、上黒川花祭りの榊鬼様は動きが激しく、省略も少なくて非常に長い。
いつかは私も…と。

「静」と「動」が常に入れ替わり、動きの流れが止まることなし。
下の写真、「かま割り」では、高く振りかぶったマサカリが、「びゃっけ」を直撃。

びゃっけに通じる神道も、すべて切断されるという…これも、恐らくは上黒川花祭り史上初。
かなりの迫力です。

立ち上る湯気がマサカリを包み、それを切るかのように素早く登るマサカリ。

終盤にさしかかると、「たい割り」といって、氏子が手に持つ松明をマサカリで打ち、

火の粉が周囲に散開。

最後には片手マサカリの所作がありますが、ここ10年は見たことがありません。
何故ならば…
私は支度部屋。
次に待つ「すりこぎ・しゃもじ」の準備です。
ギリギリまで榊鬼様を見て、舞終えた榊鬼様の介抱をしていたら、準備が…!!
大慌てで面を付けようとするも、面を付けてくれる人がいない!!
焦った。
近くにいた氏子の方をひっ捕まえて、お願いして面のひもを縛ってもらうが早いか…
しゃもじを手に持って舞庭へ。
カメラを持った「しゃもじ」さんというのもおかしいので、残念ながら写真は御座いませんが…。
今年もまた、顔が真っ黒になるくらい、味噌を顔に塗りつけさせて下さる心優しい方々がたくさんいらっしゃいました。
「すりこぎ・しゃもじ」では、面を付けたふたりが手に持ったすりこぎ・しゃもじに味噌を塗りつけて、それを会場の観衆に塗りつけるという…なんとも、笑いの絶えない演目です。
男性も、お化粧をしている女性も、関係無し!!
中には、味噌パックと言っても過言ではないほど、顔中を味噌だらけにしてしまった女性の方も…(笑)
今年こそは、味噌塗りから引退と思っていましたが、人手不足が、なかなか手放してくれません。
さて。
先ほどの榊鬼様の舞で、添え花(奉納により記名された飾り:持ち帰り可能)に付いていた名札が落ちてしまいました。さすが、上黒川花祭り史上最大の榊鬼様です。
さすがはさすが、榊鬼様。
先ほどの榊鬼様がイスもハシゴも使わずに、手を伸ばして名札をとめなおし。

事後処理までしっかり行われる榊鬼様です。
榊鬼様の向こう側、窓からは今にも朝日が差し込まんばかりに、夜明けのブルーが朝を告げています。
夜明けとともに始まる、四つ舞(扇の手)。

今年は4人のうち、3人が初めての四つ舞にチャレンジ!!
うち1人は、花祭り歴4年にして、宝の舞の次が四つ舞扇という何段も追い越してステップアップした猛者です。
完全に明け切った朝日を浴び、朝日の衣装に身を包んだ四つ舞(やち&剣の手)へと続きます。

先ほどの四つ舞扇もそうですが、
「上黒川花祭りは、女の子たちで保ってるね」
そう言われることが多くなってきました。
男女比率を比べれば、女の子の方が断然多いです。
しなやかな舞が特徴の上黒川花祭りでは、女の子が舞って違和感が無いどころか、合っているなぁと思うこともしばしば。私よりも年上のお母さんも、舞っておられます!

時代に合わせて変容していくからこそ、続いてゆき、伝統となる。
伝統とは、変わっていくもの。
かつで出会った人間国宝の方がおっしゃった言葉が脳裏をよぎります。
そして、湯囃子へ。
榊鬼様が湯囃子の舞で太鼓に初チャレンジ!!

あれだけの舞を舞った後に…長時間叩き続けるその体力に脱帽。
太鼓を叩くというのは、単に叩くだけでは無く、舞手や笛の音色を意識しつつ、目の前にある「うたぐら」を斉唱するという、マルチ且つ精神力、体力を必要とします。

一体、ひと晩の間に、何度舞を舞ったのか。
舞手にも疲労の色が見えます。

写真を見ていても、彼らは一体、何度登場しているのか…と。
しかし、フィナーレが近づくと、「その瞬間」が近づいてくることに笑顔が漏れます。

一斉に、湯がほとばしる!
4人の舞手が手に持った「たわし」が一晩中煮立てられた湯釜に突っ込まれ、一斉に引き上げると同時に湯が観衆に向けて!!
そのとき、私は釜の湯の減少量を確認しながら、前進に湯を浴びて…
第一波が過ぎ去ったところで、湯をつぎ足しに走る。
これも、大事なお役目です。
第2波、第3波と続き、全身びしょ濡れ。
極寒の中。
不思議なもので、寒さは感じません。
半袖半ズボンですが。
湯浸し、水浸しになった床面に大鋸屑を散布し、水分を吸収させて袋に詰め直す。
水分が無くなったところで、朝鬼様登場。
残念ながら…
片付け等々をやっていたら朝鬼様の写真を取り逃してしまいましたが…
実は今年の朝鬼様。
直前まで、舞手が決まらず。
直前と言っても、前日とかいうレベルではなく、湯囃子の最中に決まったくらい。
我々に鬼の舞を指南下さっている先輩が、急遽、面を付けて下さいました。
さすがです。
最後の舞、獅子舞。

これまた、私と同じ職場にIターンで就職した後輩君が後ろ足に!
Iターン人材、大活躍。
獅子舞の姿を、ずーっと目で追い続ける次男君。

長男は一晩中舞庭に、娘さんと次男君は午前様の帰宅にもかかわらず、朝から参じてくれました。

これにて、上黒川花祭りの次第は終了。
「しめおろし」があり、幕を閉じました。
その後、片付け作業が進み、ひと晩お世話になった衣装や面を蔵へしまいます。
丁寧に、丁寧に取扱い。
終わって解散となったのは午前11時頃。
その足で、目の前にある日帰り温泉、パルとよねへ。
全てを洗い流しました。
もちろん、お風呂には花祭りを共に過ごした面々もあり、プチ反省会。
いちの舞で頂いた御利益が身体中に残っていて、そのすさまじさを垣間見ました。
クタクタ。
もう、お昼ご飯を食べる力も残っておらず、そのまま布団に入った午後1時。
これ以上無いほどの深い眠りに落ちて、目が覚めた午後4時。
うん。
回復した。
よし、行くぞ!!!

来ちゃいました。
豊橋市の御幸神社で毎年、1月4日に行われている花祭り。
佐久間ダムの建設に伴い、豊根村から豊橋市へ入植した人々により、守り続けられてきた花祭りです。
これまでずっと、上黒川花祭りが終わったその日の夜なので…行くことをためらっていました。
しかし、今年は休日の巡り合わせが非常に良い!!
御幸神社花祭りか、富山御神楽祭りか、どちらかへ行こうと考えていました。
妻等々意見を集約して出た結論。
未だかつて行ったことがない、御幸神社花祭りへ行こうと。

子どもたちも皆連れて行ったら、次男君が味噌を塗られてトラウマレベルの泣きじゃくり。

下黒川花祭の方々も多数舞庭にいらっしゃり、全くアウェイ感がありませんでした。
初めて来たにもかかわらず、地元のような感覚。
豊根村出身の花祭りですから、舞のところどころが似ていることも、そう思わせるのでしょう。

人生初の、1日で2回目の湯囃子を体験。
次男君も、もはや慣れたもの。
抱っこしながら写真を撮っていましたが、全く動じない。

御幸神社の近くには、しょっちゅうこのブログに登場される私の伯父さまが住んでおり、一緒に花見物しました。
「なんだ!!けんたろーー!!上黒川の花が終わってから来たのかーーー!!!」
何度言われたか。
それくらい、上黒川花祭り人間がこの場にいることが驚異的???
確かに。
帰りの車で疲労感が一気にやってきました。
栄養ドリンク片手に、無事、自宅まで到着した午前1時。
例年になく、楽しい正月休みになっております。