国道、県道、市町村道などといった公道にある橋梁は、5年に一回の定期点検が義務づけられました。
平成26年度から!
今年で、豊根村内にある村道の橋梁定期点検は完了する予定ですが、素人で判断するわけにもいかないため、現状では専門家であるコンサルタントに数千万円のお金をかけて委託しています。
しかし、それももったいないといえば、もったいない。
大きな橋梁は橋梁点検車両などが必要になりますが、小さな橋梁で河川からの高さが低いものであれば…自分たちでもやれるんじゃない!?
そーすれば、数百万円くらいは経費削減できるかもしれません。
その手法を学ぶため、愛知県の専門家に、豊根村まで来て頂きました。設楽町の方々ともコラボレーションで!今日は豊根村、明日は設楽町。
対象となる橋梁はこちら。

見た感じからしてボロボロですが、昭和25年に架設された橋梁にしては健全という判断です。
基本的に、点検者が手を伸ばして届く距離で確認せねばならない(近接目視)のため、はしごなどを駆使してひとつひとつの部材を確認していきます。
そして、懸念のある損傷部位についてはチョークでマーキングして写真を撮り、後々、台帳にまとめます。

上の写真は舗装表面。
下の写真は床板裏で発見された穴と豆板。

川の中に入ってはしごに登って、ハンマーを使って部材をひたすらたたきます。
たたくことでその音を確認し、コンクリートの中身がちゃんと詰まっているかを判断。
浮いていたり空洞があったりすると、低い音になって返ってきます。
また、当初からの施工不良を発見することも…。
水深が深いところもあるので、胴長を着用しましたが、これがまた…
暑い!!
すべての点検が終わって胴長を脱いだところ…下半身は汗でびしょ濡れに。
洗濯直後のズボンのようになっておりました。
やはり、現地現物。
これまで、橋梁点検の座学研修は受けてきましたが、現場は全く違います。なにより、自分で判断せねばなりません。
このときに役立ったのが、過去に自分が発注した橋梁補修工事の経験。補修工法を知っていると、不具合を発見したときに、ただ不具合として認識するだけで無く、どうやって補修したら良いか?まで考えることが出来ます。
夕方までしっかり学び、定時後、点検作業の慰労会、意見交換会を兼ねて津具の「みのや」さんで実施!
建設事業について、夜の深まりとともに理解も深まりました!



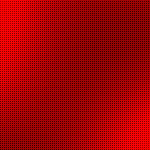
「村の橋をハンマーで叩いて点検」への1件の返信